義肢装具関係のことをガッツリと書きたいと思っているのですが、もう少し材料が必要なので、今回もあまり関係のないことを書きます。
「みんないっしょにぱらいそさ いくだ!」
これは諸星大二郎という漫画家の書いた「生命の木」の中のセリフの一つです。東北のある場所に隠れキリシタンの里があってそこで事件が起きるという内容の話です。
この話には元ネタがあり、それが「天地始之事」という長崎県に実際にいた隠れキリシタンに伝わる聖書のことです。指導者もなく、聖書のないことから、キリスト教が日本に口伝で伝わって独自の変化をしてしまったものです。天地の始まりから楽園=囲われた安全な場所からの追放、そして、ぱらいそという言葉も独特ですが、隠れた信仰生活の中でもいつかぱらいそという新しい場所に行けるというお話はとても面白い記録だなと思います。
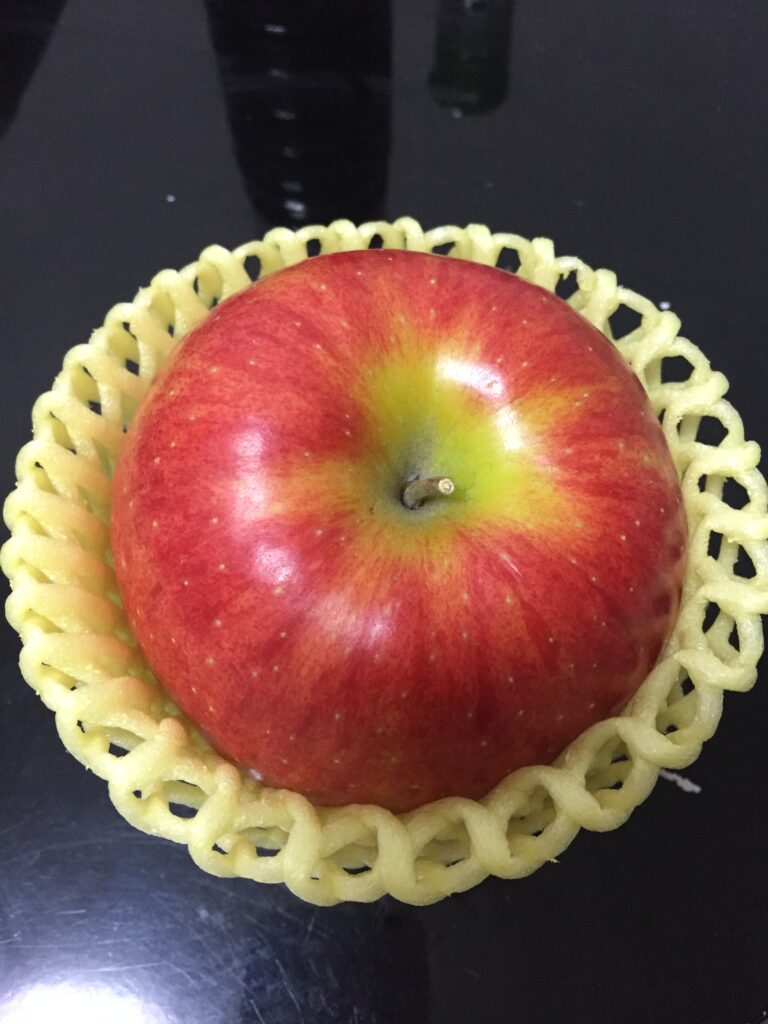
これ自体は何も関係がないような話ですが、
私がブログで関係のないことを書くのには理由があります。それは情報の新奇性が必要だと考えているためです。
脳は常に新しい情報を求めます。それは新しい情報というものが生存の確率を高めてくれるからです。一つの環境に適応することも重要ですが、危険を回避するためには常に新しい情報を取り入れている必要があります。つまり、新しい情報を欲することは生きるための本能的な力というわけです。
外国や旅行に行って異国情緒を味わいたい、都会に出てきて働きたい、ディズニーランドやUSJに行きたい。こういった感情もそこにある情報が普段の状態とは違った新しい情報に囲まれていることも大きな理由です。
アーティストの荒川修作さんの建築では、普段私たちが得ている情報の中にあえてズレや揺らぎを押し出したものを制作しています。
例えば、「養老天命反転地」では建物内の机や壁、天井といったものが上下左右を全く無視した場所に配置などがされています。
こうした場所の狙いは一歳の幼児に戻るような体験を通して、死なないことを体験することです。私たちが一歳の幼児だったころは世界が全く新しい情報で溢れていました。ドアの取手やお風呂の深さ、道を流れる景色など全てが新しい体験でそれこそが若さでした。成長する=そのような情報に当たり前に触れることで、それがどういったものなのかわかる代わりに、情報の新奇性というものが失われていくことで、日々の生活を送ることができるようになっていきます。その行き過ぎた例として、急に老人ホームなどのバリアフリーな環境に囲まれることで逆に元気がなくなってしまうようなことがあるかもしれないせん。
肉体的に幼児に戻ることはできませんが、体験として新しい情報を取り入れることで心の若さをとり戻すことが狙いのようです。
コロナウイルス蔓延では人々の”移動や行動”が大きく制限されてしまいました。これは人の本来の情報の新奇性を求める欲求が制限されていたことだと思います。もしスマホなどの情報端末がなかったら自粛生活はより窮屈なものになっていたと思います。
ブログや生活でも同じことが言えると思います。義肢装具士は義肢装具のこと、仕事のことだけに関わり、その中で新しい情報に触れるというのも合理的で試験の前などの生存をかけた戦いの前には重要だと思いますが、よりよく生きるあるいは若々しく生きるには、人間あるいは脳本来のことを考えると、常に新しさ=新奇性もとても重要な要素だと思います。それが天地の始まりから知恵の実と永遠の実=生命の木の下にいた時から変わらないことなのかもしれません。
次回は足のこととか あるいは関係ないこと書きたいなと考えています。